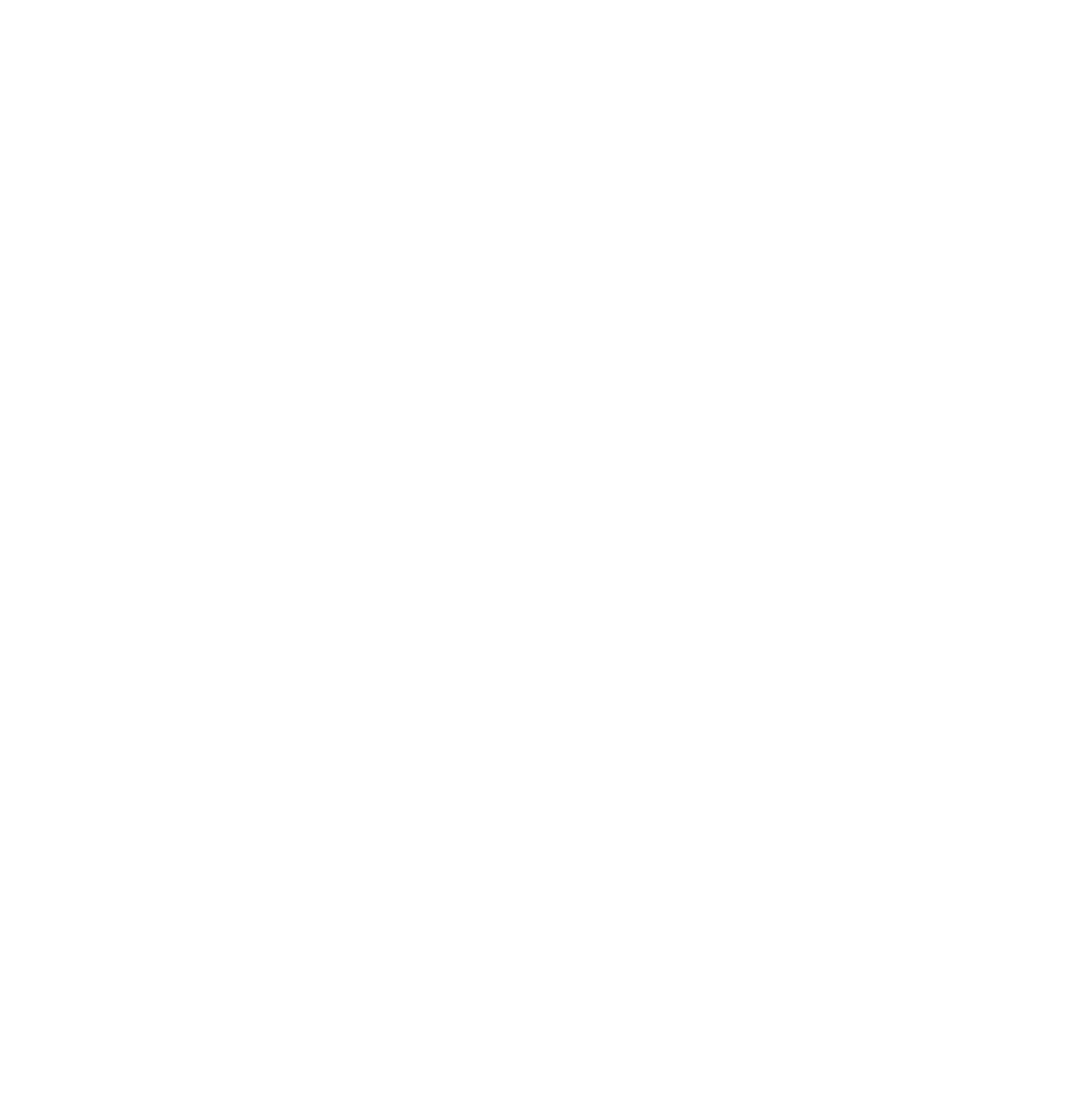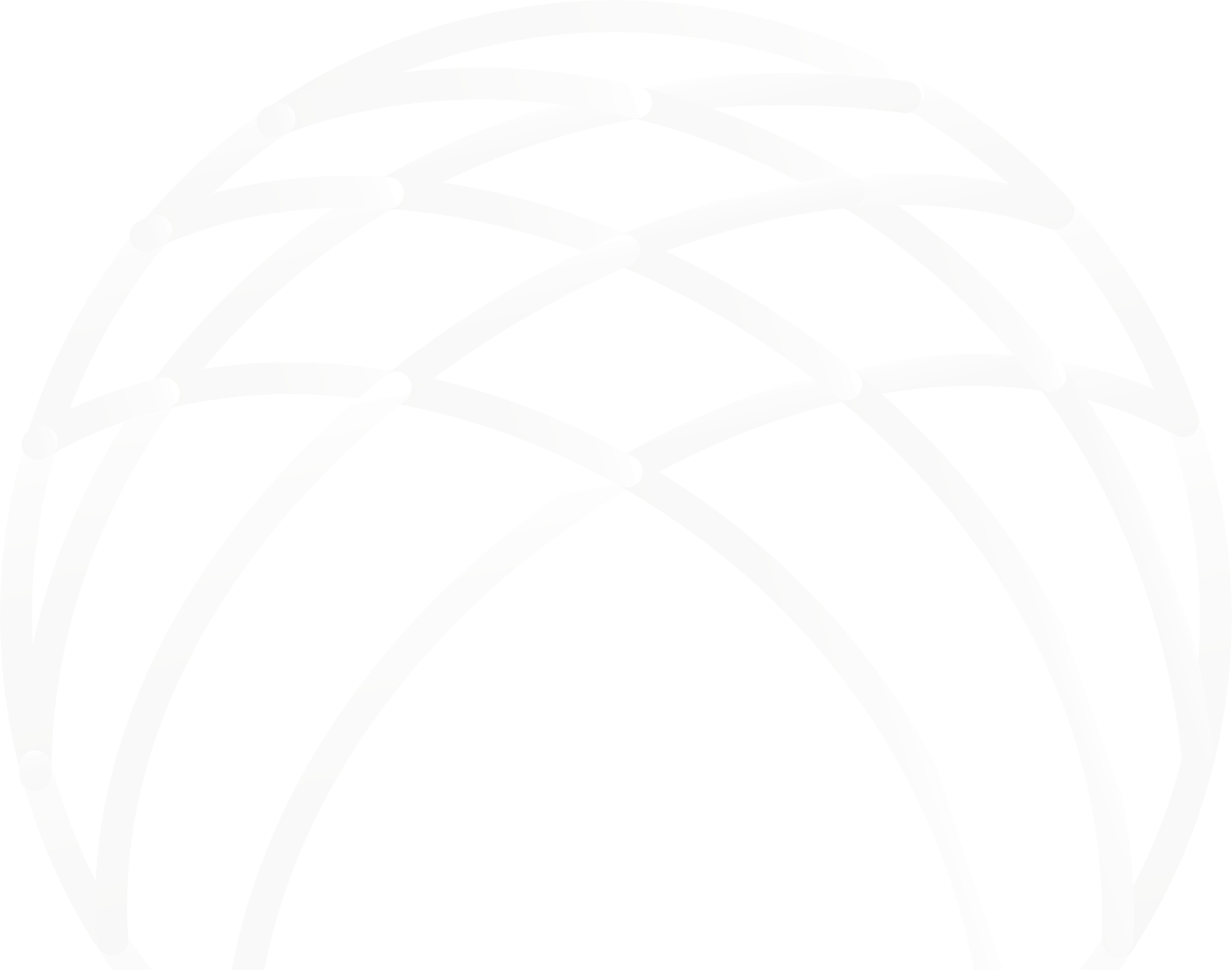グローバルリスク研究センターに、2025年10月1日付けで特任研究員が2名着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
着任の抱負
〇特任研究員 岩間春芽
この度、特任研究員に着任した岩間です。大別すると、私はこれまで2方向の調査研究を行ってきました。1つ目は、ネパール北西部農村での生計活動についての調査研究、2つ目は在留ネパール人の生計活動と生存戦略についての調査研究です。ネパール人の方々は、ネパールでも日本でも他の国でも、様々なリスクのある脆弱な環境にありながら、グローバルな人やモノの移動の流れに乗り、自らの生活を成り立たせるべく、日々戦略を練りながら生活しています。
ネパール北西部はインフラが整っておらず移動が困難で、国際機関等からは食糧不足の地域であるとされてきました。二国間援助で日本の政府備蓄米や、WFPの援助米の配給もなされてきました。しかし、長期間その地域に滞在し、地域住民の話を聞き、データを集めていくと、話はそう単純でもないようだということが見えてきました。今年は日本で備蓄米が放出されたため、ネパール北西部に送られない可能性もあります。その場合、地域社会ではどのような変化が起こるのか、時間と費用が許すならば、追っていきたいです。
近年、日本で町の中華料理屋ならぬ、町のインド料理屋が全国的に増加し、身近な存在となってきています。噂されている通り、インド料理店で働く料理人や経営者の多くはインド人ではなくネパール人です。在留ネパール人はこの10数年間、増加傾向にあり、20万人を超えています。インド料理店で働く料理人と経営者の生計活動と生存戦略についての論文は、某所のインド料理店で働きながら調査しデータをまとめたものです。数年かかりましたが、なんとか学会誌に掲載されました。詳細はこちらをご参照ください。
在留ネパール人が急増した一因として、インド料理店で働く料理人(技能ビザ)や経営者(経営管理ビザ、永住者)の家族の家族滞在ビザが認められるようになったことが挙げられます。ネパール人の親たちはより高い賃金が得られる日本に来たものの、ネパールでは幼少時からの英語教育が盛んで、親族家族が英語圏の国にいることもあり、いずれは英語圏の国に移住したいと考える人が少なくありません。
こういった親の姿勢は子供にも影響します。子供は学齢期の途中で日本の公立校に転入してほぼ毎日学校に通うものの、日本語を熱心に学び同級生の学習レベルに追いつけるとも限りません。子供たちは日々嵐を巻き起こしながら、強くたくましく誇り高く学校生活を送ります。親のビザの都合等で突然転校していなくなり、学校は「嵐が去った」状態となります。子供たちは親の都合に振り回されているようにも見えますが、彼らなりに日本の公立校で得られるものを得て、使えるものを使っているという主体性も感じられます。
留学生として来日し、日本語学校、専門学校を経て就職するネパール人の若者も増加しています。初期は大都市圏が主でしたが、近年は地方都市でも増加し、駅近くのコンビニで買い物をすると、留学生らしき若者から接客を受けることも少なくありません。ネパール人留学生はホテルや飲食チェーン、自動車整備、介護など、労働環境が厳しい人手不足の業界に就職する傾向がありますが、彼らは「日本にはチャンスがある」と口を揃えます。彼らが日本でどう生き残っていくのか、将来どうしていくのかも追っていきたいと考えています。
〇特任研究員 塩出綾
このたびグローバルリスク研究センター特任研究員に着任しました塩出綾です。これまで長年に渡り、ラテンアメリカの多様な民族・言語・文化環境で生活してきました。その中で、北米と南米の間に位置する中米地域の移民について関心を持ち、コスタリカのコーヒー収穫を担うニカラグア人とパナマの先住民に焦点を当て、中米域内の外国人農業労働者の移住メカニズムに関する実証研究をしています。
さて、日本にいる私たちの生活とは一見無縁に思われるこのテーマは、グローバルリスク研究とどう関係があるのでしょうか。環境問題や争い等により、世界のどこにいても命の危機があり得るグローバル化した今日において、生命維持の基本である食べ物の生産と確保は、誰もが考えずにはいられないイシューとなりました。ここで注目すべきは、ここ数十年で、日本を含む多く国々において、食べ物生産、つまり、農業分野の人手の移民化が進んでいる点です。EUでは、毎年、約80~100万人の外国人季節労働者が農業セクターを中心に雇用されています。また、米国でも、農園労働者の約7割が国外出身者です。更に注視したいのは、この人たちの生活・仕事・移動の実態です。複数の先行研究によれば、世界的課題である食料生産を支える移民労働者は、不安定な立場にあります。私たちが住む日本でも、農業分野にアジア諸国の若者が外国人技能実習制度等の下で就労しており、その制度や労働内外の環境がしばしば議論の対象となってきました。その制度の是非はさておいたとしても、日本の食料生産もまた、外国人労働者に頼っているのが実情です。同時に、日本は食料の多くを輸入に頼っているため、遠く離れた外国の畑の人手事情が私たちの食卓に影響を及ぼしかねません。
実際に、パンデミック中には多くの国で人の移動が大幅に制限され、農業分野の外国人労働者や家族、その雇用者たち、そして、その生産によって生活をしている私たち消費者や消費システム等も影響を受けたり、受ける危機にあったりしました。私の調査地のコスタリカでも、国境が封鎖され、コーヒー収穫を行う外国人労働者の確保が社会問題化しました。このように、コロナ禍の身近な経験だけを見ても、食べ物生産の人手に関する議論は、「食料システム」や「フードシステムリスク」だけでなく、「感染症」や「グローバル化」や「社会の二極化」等、多数のグローバルなリスクが複雑に絡み合うテーマだと言えるでしょう。だからこそ、命の基本である食料の生産をいかに実現するのかについて、世界共通の「グローバルリスク」課題として、多角的に取り組んでいくことが求められているのではないでしょうか。
国内外のアカデミア、また、官民での実務者としての勤務経験も活かしつつ、自然と文化が豊かなこの地で、学内外のみなさまと手を携えて研究ができることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。